第1分科会 公共図書館
テーマ「地域社会における公共図書館の存在意義」
誰でも使える公共施設として全国の自治体が整備を進め、多くの利用者に活用されている公立図書館だが、建物の整備が進められる一方で、行政サービスとして何を住民に保障していくべきか、そのためにどのような資源が必要か、社会の中でその役割をどのように位置づけていくべきか、そもそも行政サービスとして提供すべき機能であるかと、あらためて問い直される状況がある。
コロナ禍では、公立図書館の必要性が強調されながらも、不要不急の施設として、利用を制限する動きに対して強い異議はなく、代替サービスの提供も十分ではない。
民主的な社会になくてはならない施設としてのあり方を考える。
基調報告
小泉 公乃 (筑波大学図書館情報メディア系准教授)
「欧米の事例からみる民主主義と図書館」

小泉 公乃 (こいずみ まさのり)
筑波大学図書館情報メディア系・准教授。博士(図書館・情報学)。慶應義塾大学文学研究科助教、ピッツバーグ大学大学院情報学研究科客員研究員を経て、2015年4月から現職。代表的な学術書は Inherent Strategies in Library Management(2017)。同著作は2018年度日本図書館情報学会賞を受賞。
事例報告
横山 ひろみ (瀬戸内市民図書館主幹)
「広場としての図書館」

横山 ひろみ (よこやま ひろみ)
瀬戸内市民図書館は、2021年6月1日に、開館5周年を迎えました。
今回の事例報告では、この5年間を振り返ると共に、コロナ禍だからこそ、改めて、図書館サービスの在り方を考えてみたいと思っています。
事例報告
淺野 隆夫 (札幌市中央図書館利用サービス課長)
「おしごとからわたくしごとまで ~はたらくをらくにする課題解決型図書館の挑戦」

淺野 隆夫 (あさの たかお)
札幌市 中央図書館 利用サービス課長
2014年に「札幌市電子図書館」を立ち上げた後、「札幌市図書・情報館」のコンセプトづくりに着手、2018年の開館と同時に初代館長を務める。同館がライブラリーオブザイヤー2019の大賞とオーディエンス賞を受賞。2020年から現職となり、中央図書館の業務も併せて所管。この9月からは北海道武蔵女子短期大学で司書課程の講義も受け持つ。また、総務省情報化アドバイザーとして全国の新しい図書館づくりにも参画している。
事例報告
やまなし読書活動促進事業実行委員会 (代表者 須藤 令子)
「やま読を楽しめ! ―わたしと本とあなたと―」
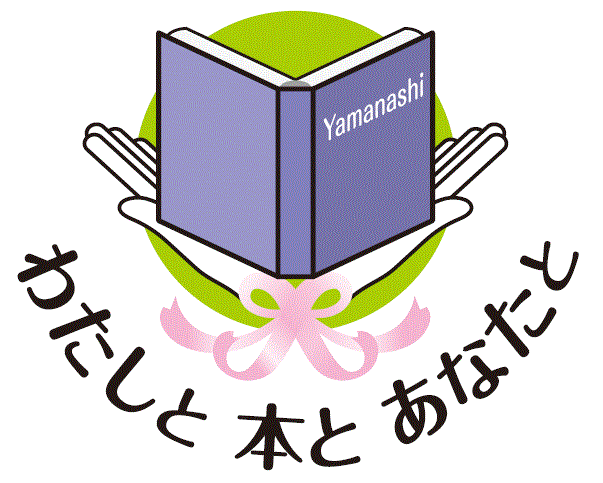
やまなし読書活動促進事業
やまなし読書活動促進事業は、家族や友人、親しい人などに本を贈る習慣を広め、県民一人ひとりの読書への関心を高めることにより、読書活動の推進を図ることを目的としています。本事業では、地域の書店や図書館が連携して様々な取り組みを行い、読書のすそ野を広げようと活動しています。
事例報告
小佐野 みはる (富士吉田市立図書館課長補佐)
「図書館というパフォーマンス (図書館を見せる)」

小佐野 みはる (おさの みはる)
「らしくない図書館」を合言葉に、誰もが楽しめる富士吉田市立図書館らしい空間を作り続けている。
本が好きな人も苦手な人も、ワクワクに出会える場所でありたい!
意見交換
小泉 公乃、横山 ひろみ、淺野 隆夫、須藤 令子、小佐野 みはる
司会:成瀬 雅人 (原書房)